顧客へのアプローチ手法の一つである紙媒体のDM(ダイレクトメール)。アナログ的な手法ですが、開封率の高さや表現の幅広さは電子メールにはないメリットです。一方で電子メールと比べると費用や時間がかかるというデメリットがあり、中小企業には取り組みづらい一面があることも否定できません。
そのような課題を解決できるのが「小規模事業者持続化補助金」です。要件を満たして申請し、採択されれば最大50万円(特例を利用すれば最大250万円)の補助金を受け取れます。本記事では、DMのメリットやデメリット、小規模事業者持続化補助金の申請の流れや注意点を解説します。
DMを使った施策がビジネスに有効な理由とは?
DMは、個人や法人の顧客に直接メッセージを送るマーケティング手法です。広い意味でのDMには電子メールなども含まれますが、一般的には紙媒体のものをDMといいます。紙媒体のDMの主なメリットは以下の4点です。
開封率が高い
紙媒体のDMの大きなメリットとして、開封率が高いことが挙げられます。一般社団法人日本ダイレクトメール協会の「DMメディア実態調査2021」によれば、自分宛に届いた紙媒体のDMの開封率は79.5%でした。また、開封した上で何らかの行動(インターネットで調べる、商品を購入するなど)をした人の割合は21.0%で、開封したが何もしなかった人の割合は58.5%でした。
電子メールの場合はどうでしょうか。BENCHMARKの「平均メール開封率・クリック率レポート(2024年版)」によれば、日本の電子メールマガジンの開封率は31.75%、クリック率は1.30%でした。調査年度は異なりますが、紙のDMは電子メールと比べて、目を通してもらいやすいと考えられます。
参考:一般社団法人日本ダイレクトメール協会.「DMメディア実態調査2021」.
https://www.jdma.or.jp/upload/research/20-2022-000021.pdf ,(参照2025-8-6).
参考:BENCHMARK.「平均メール開封率・クリック率レポート (2024年度版)」.
https://www.benchmarkemail.com/jp/email-marketing-benchmarks/ ,(参照2025-8-6).
表現の幅が広い
DMは電子メールと比べて表現の幅が広く、顧客の属性に合わせた色やフォント、イラストなどを利用できます。例えば女性向けの場合は華やかなデザインにする、中高年向けの場合は文字を大きくして読みやすくするなどの工夫も可能です。
さらに、DMでは視覚以外の五感に訴える広告も作れます。特に多いのが嗅覚に訴える広告で、例えば製品の香りを封筒やパッケージに加えることで、効果的に受取人の興味を引くことが可能です。
直接顧客の手元に届く
DMは、顧客の年齢や性別、購入履歴などを元にカスタマイズした情報を直接届けられます。顧客の立場からは、カスタマイズされた情報は「自分のためだけに用意されたもの」に見えるため、顧客満足度を高めやすいです。適切な案件管理システムを使えば、顧客の属性に合わせたDMを効率的に送れます。
効果測定ができる
紙媒体のDMの開封率を直接計測するのは難しいですが、開封した顧客がどのような行動を取ったかはある程度測定可能です。例えばDMにQRコードを記載して、DM送付数に対するアクセス数の割合を計測すれば、どれくらいの顧客がDMを開封し、その内容に興味を持ってくれたかが分かります。
効果測定は結果を計算して終わりではなく、次の施策につなげることが大切です。デザインが異なる2つのDMを用意して反応を比較し、より反応が良かったデザインをベースに改良を重ねることで、成果を高めていけます。
効率的に施策を行いたい場合は、専門のDM効果測定サービスを利用するのもおすすめです。「DM+」ならQRコードを活用した効果測定ができる他、DMの作成・発送までお任せいただけます。

DMを使った施策における懸念点
ここまで紹介してきた通りDMにはさまざまなメリットがある一方で、懸念点もあります。DMのメリットと懸念点の両方をよく比較し、本当にDMを導入すべきなのか慎重に検討しましょう。
費用と時間がかかる
紙媒体のDMは、電子メールと比べて費用と時間がかかる手法です。顧客の分析やリスト作成に加え、印刷物のデザイン作成、発注、封入、郵送の手続きといった工程に手間と経費が発生します。また、DMを企画してから顧客に届くまでの時間もかかるため、情報が届く頃には鮮度が落ちてしまうリスクもあります。
顧客データの入手と精査が必要
DMの送付のためには、当然ながら顧客データが必要です。しかし現代の日本で住所や氏名などの個人情報を顧客から得るのは容易ではなく、入手した後も慎重な取り扱いが求められます。また、顧客データは常に最新の状態に保ち、必要なときに精査しやすいようにまとめておく必要があります。
反応があるまで時間がかかることも
DMを受け取った顧客が、すぐに反応してくれるとは限りません。そもそも顧客が郵便受けを毎日見るとは限らず、手に取っても「後で見れば良いや」としばらく放置されるケースもあります。電子メールやWeb広告と比べると、結果が出るまでに時間がかかる点は理解しておきましょう。
DMに活用できる「小規模事業者持続化補助金」とは?
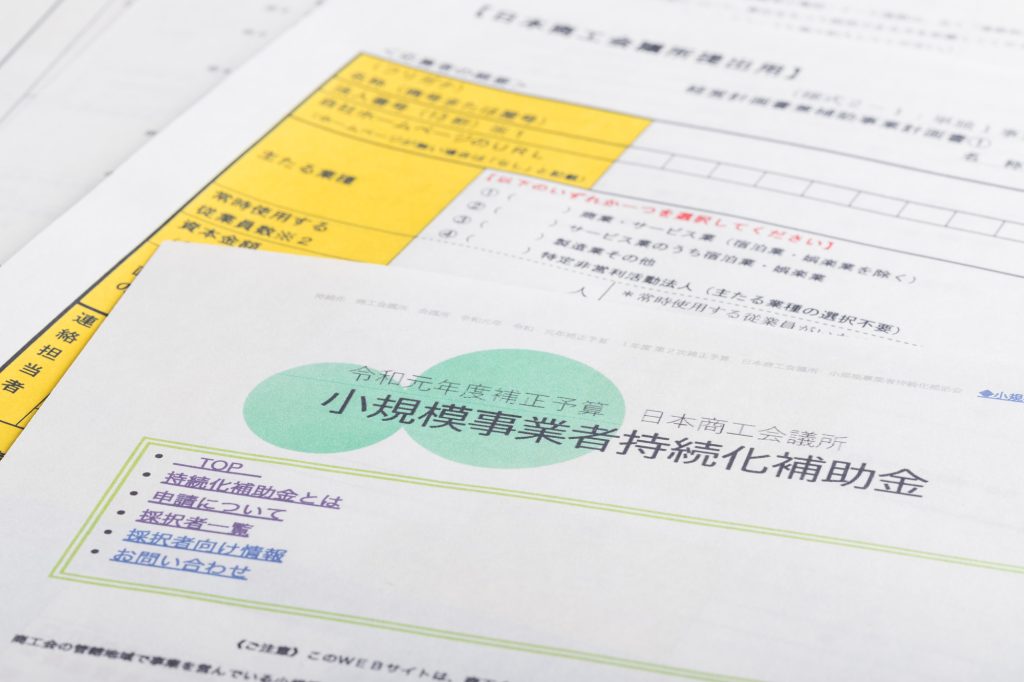
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の販路開拓や生産性向上を対象とする補助金制度です。DMの送付費用などは「広報費」として補助金を申請できます。年に数回募集が行われており、2024年8月に公開された第16回公募では、7,371件の申請のうち2,741件が採択されました。
参考:中小企業庁.「小規模事業者持続化補助金(第16回締切分)」の補助事業者が採択されました」.
補助上限額・補助率
DMの送付費用を対象とする場合は、基本的に「小規模事業者持続化補助金(通常枠)」に応募します。通常枠の補助上限額は50万円(賃金引上げ特例などの特例を利用した場合は最大250万円)、補助率は2/3です。
参考:中小企業庁.「小規模事業者持続化補助金(通常枠)」.
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_jizoku.pdf ,(参照
2025-08-06).
参考:中小企業庁.「持続化補助金の概要」.
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_jizoku_summary.pdf ,(参照2025-08-06).
補助金の対象事業者
補助金の対象事業者は以下の通りです。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員が5人以下
- サービス業(宿泊業・娯楽業):常時使用する従業員が20人以下
- 製造業またはそれ以外の業種:常時使用する従業員が20人以下
なお、医療法人や宗教法人、学校法人などは対象になりません。
参考:中小企業庁.「小規模事業者持続化補助金(通常枠)」.
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_jizoku.pdf ,(参照2025-08-06).
参考:中小企業庁.「持続化補助金の概要」.
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_jizoku_summary.pdf ,(参照2025-08-06).
補助対象となる経費
小規模事業者持続化補助金の対象となる経費は以下の通りです。
- 機械装置等費
- 広報費
- Webサイト関連費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 新商品開発費
- 借料
- 委託・外注費
前述の通り、DMにかかる費用は広報費として申請できます。その他、新聞や雑誌への広告掲載費、チラシやカタログの外注・発送にかかる費用なども対象です。
参考:中小企業庁.「小規模事業者持続化補助金(通常枠)」.
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_jizoku.pdf ,(参照2025-08-06).
参考:中小企業庁.「持続化補助金の概要」.
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_jizoku_summary.pdf ,(参照2025-08-06).
小規模事業者持続化補助金の申請の流れ
小規模事業者持続化補助金は、以下の流れに従って申請してください。
- 各書類の作成
- 商工会議所に「事業支援計画書」の交付を依頼
- 申請書類の提出
- 審査と採択・不採択の決定
- 補助事業の実施(採択された場合)
- 実績報告書の提出
- 補助金額の確定
- 補助金の請求
- 補助金の入金
- 事業効果の報告
各書類の作成
小規模事業者持続化補助金を申請する際には、以下の書類が必須[A1] [A2] です(2025年8月時点)。いずれも小規模事業者持続化補助金のWebサイトからダウンロードできます。
- 持続化補助金事業に係る申請書
- 経営計画書兼補助事業計画書①
- 補助事業計画書②
- 補助金交付申請書
- 宣誓・同意書
上記に加えて、申請者の形態(法人・個人事業主・NPO等) によって、会計書類や会社の基本資料も添付が必要です。例えば法人の場合は、直近1期分の貸借対照表や損益計算書、株主名簿などがあります。必要書類が分からない場合は問い合わせし、スケジュールに余裕を持って全ての書類を完成させておきましょう。
商工会議所に「事業支援計画書」の交付を依頼
補助金申請の際には、前述の書類に加えて「事業支援計画書」が必要です。営業地域を管轄する商工会議所(例:23区内の場合は東京商工会議所)から交付を受けましょう。
交付の際には面談があり、担当者が申請内容、計画の妥当性、実現性などをチェックします。内容に問題がなければ、事業支援計画書を受け取れます。時間がかかる場合もあるため、早めに行動しましょう。
申請書類の提出
書類が全てそろったら受付期間中に提出しましょう。以前は郵送でも提出できましたが、第18回(2025年10月3日受付開始)では電子システム(Jグランツ)からでないと提出できません。Jグランツの利用にはgBizIDプライムアカウントの取得が必要で、申請から取得に3~4週間かかるため、早めに準備しましょう。
審査と採択・不採択の決定
提出した書類を、専門の審査員が審査します。書類に不備がないか、事業の目的や成果が補助金制度とマッチしているか、計画実現性はあるかなどがチェックされます。採択されたら、その後の手続きに関する案内を受け取ってください。
補助事業の実施(採択された場合)
申請が採択されたら手続きに沿って進め、補助事業を実施します。補助金は経費の支払いよりも後で受け取ることになるため、事前に手元資金を用意しておきましょう。補助対象となる経費と自己負担すべき経費は正確に管理し、領収書などの証拠書類をそろえておきましょう。
実績報告書の提出
補助事業が終わったら、実績報告書[A3] を作成して指定された宛先まで送付します。実績報告書は事業の成果や補助金の利用状況をまとめたものです。書類に不備があったり、領収書などの証拠書類が不足していたりすると、補助金が受け取れなくなるかもしれません。また、締め切りは必ず守りましょう。
補助金額の確定
実績報告書や証拠書類を元にした審査が行われ、それを元に補助金額が決まります。対象外とされた経費や、証拠書類が不足している経費は、補助金の対象とならないことがあります。必要に応じて追加書類の提出が求められることもあるので、迅速に対応しましょう。
補助金の請求
補助金額が確定したら、補助金を請求する手続きを行います。補助金交付申請書[A4] を様式に従って記入し、必要書類を添付して提出してください。請求から入金まである程度時間がかかるため、この期間の資金繰りのこともあらかじめ考えておきましょう。
補助金の入金
請求手続きが終わったら、補助金が入金されます。速やかに記帳しましょう。
事業効果の報告
補助金を受け取った後は、事業効果を報告しなければなりません。これは補助金を活用して実施した事業で得られた成果(売上や顧客数の増加、経費の削減など)を報告する手続きです。報告の際に成果を証明する資料の提出を求められることがあるので、その場合は速やかに提出してください。
DMに補助金を活用する際の注意点

DMに補助金を活用する際は、以下の点に注意するとトラブルが起こりにくくなります。
申請期間や要件を必ず確認する
小規模事業者持続化補助金は申請期間と要件が定められています。例として、第18回公募の公募要領公開は2025年6月30日、申請受付開始は2025年10月3日、申請受付締切は2025年11月28日です。なるべく公募要領公開直後にスケジュールや要件を確認し、早めに書類を完成させておきましょう。
書類作成は入念に行う
書類に漏れや不備があった場合、要件を満たしていても補助金が支給されないことがあります。よくある不備は以下の通りです。
- 指定形式以外のファイルで提出している
- ファイルにパスワードが指定されている
- 記入日が記載されていない
- 書類ごとに代表者名が異なっている
なお、小規模事業者持続化補助金の申請代行は認められていませんが、識者からアドバイスをもらうことは問題ありません。不安な場合は士業や商工会議所などに相談しましょう。
要件を満たしても採択されない可能性がある
小規模事業者持続化補助金は、要件を満たしていれば必ず受け取れるわけではありません。小規模事業者持続化補助金の予算には上限があり、評価が高い事業者から順に補助金を割り当てる仕組みです。たとえ要件を満たしていても、事業計画に難があったり、実現可能性が低いと見なされたりすれば順位が下がるため、採択されにくくなります。
補助金交付決定前に施策を開始しない
補助事業は必ず、補助金の交付が決定してから始めましょう。補助金の対象になるのは補助事業実施期間中に実施した事業だけですので、交付決定前、もしくは事業期間終了後の経費は全て対象外となります。なお、補助事業実施期間の長さは通常半年程度です。
申請から入金までに時間がかかる
小規模事業者持続化補助金は、申請してから実際に補助金を受け取れるまで約1年かかります。補助対象の経費であっても一度自分で立て替える必要があるため、十分な手元資金を作っておきましょう。
まとめ
紙媒体のDMを活用したアプローチは開封率が高く、効果測定ができる点が大きなメリットです。一方で電子メールなどと比べると費用や時間がかかる、すぐに反応を得られないなどのデメリットもあります。費用の負担が重い場合は、小規模事業者持続化補助金の活用を検討すると良いでしょう。申請には手間はかかりますが、経費の2/3を補助してもらえるのは中小企業にとっては大きな支援となります。
また、DMに関連する業務の効率化・高収益化を目指す方におすすめなのが「DM+」です。顧客個人の行動を可視化し、効率的な集客・データ管理・分析を実現します。シンプルで低価格な複数のプランの中から、最適なものを選べるため、幅広い事業者に対応可能です。どれを選べば良いか分からない方も、まずはお気軽にご相談ください。




